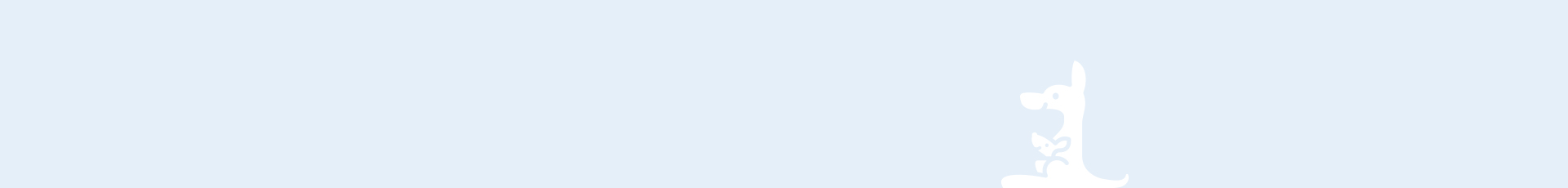
アレルギー診療
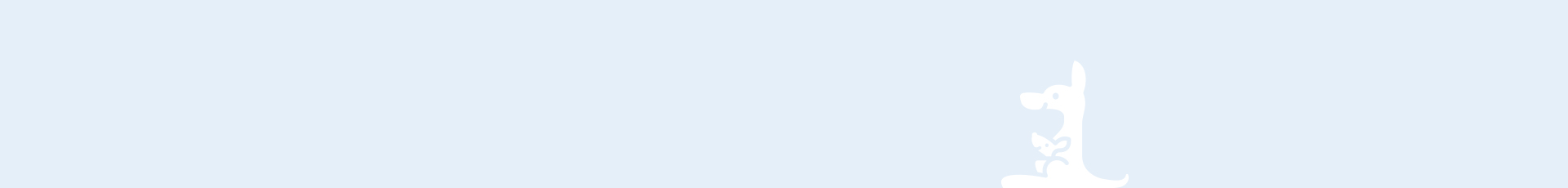
アレルギー診療
体には「免疫」という病気を引き起こす異物(細菌やウイルスなど)から体を守る防御機能があります。この防御機能がダニや花粉、食物などに対して過剰に反応して、はなみずや湿疹、目のかゆみなどの症状を引き起こす状態をアレルギー反応といいます。
特定の物質にさらされることで、「くしゃみ」「はなみず(特に透明でサラサラした)」「鼻づまり」の症状がでることをアレルギー性鼻炎といいます。原因にはダニやハウスダスト、花粉、イヌ・ネコのフケなどがあります。
アレルギー性鼻炎の中でも、花粉が原因で症状がでるものをいいます。小学生の3人に1人、中学生の2人に1人は花粉症と言われています。花粉もいろいろありますが、日本では7割以上がスギ花粉症です。診断は、原因となる物質にさらされると症状がでることの確認、検査(血液やはなみず)を合わせて行います。治療は原因物質を避けること、対症療法、免疫舌下療法などがあります。
免疫舌下療法はスギアレルギーとダニアレルギーに対して行うことができます。
免疫舌下療法は、アレルギーの原因となる物質を毎日少量投与(舌の下にのせて吸収させる)することで、アレルギー反応をやわらげていく治療です。根本的な体質改善が期待できる治療法です。
当院で免疫舌下療法の導入、継続治療を行っておりますのでご希望の方はお越しください。
※現在、スギアレルギーの治療薬が全国的に不足しており、ご案内ができない可能性もございます。
正式には、気管支喘息といいます。ぜんそくは、空気の通り道である気道(気管支)がさまざまなきっかけで発作的に狭くなってしまうことを繰り返す病気です。
症状は、ゼーゼーやヒューヒューといった音がする喘鳴(ぜんめい)や息苦しさです。この状態を「ぜんそく発作」と呼びます。
治療は
があります。
以前は、2〜3歳ごろにぜんそくを発症するお子様が多いとされていましたが、最近では0歳でぜんそくと診断されるお子様も増えています。
ぜんそく発作を繰り返すと気道の壁が厚く硬くなります。これを「リモデリング」と呼びます。気道のリモデリングはぜんそくの発作がおきやすくなり、ぜんそくの難治化につながります。
アトピー性皮膚炎は、強いかゆみのある湿疹が悪くなったり良くなったりを繰り返す皮膚の病気です。特徴として、皮膚のバリア機能が低下し、水分が失われやすく乾燥肌になります。
乳児では顔や頭がカサカサして赤くなり、幼児では目や耳の周り、首、ひざやひじの内側などに湿疹ができやすいです。湿疹によるかゆみによって、夜眠れなくなり成長障害や日中の睡眠不足による集中力の低下など日常生活に大きな支障が出てしまったりする可能性もあります。
治療は
が基本になります。
目標は日常生活に影響がないように症状を最小限に抑え、その状態を維持することです。皮膚の見た目が改善したからといって治療をやめてしまうと、また症状がぶり返してしまうので注意が必要です。
特定の食べ物を食べると症状がでることをいいます。乳児期にもっとも多く、乳児期は卵、乳製品、小麦が原因のほとんどです。学童になると甲殻類(カニやエビなど)、魚卵(イクラなど)、木の実(ピーナッツやアーモンド、くるみなど)が原因の食物アレルギーが増えていきます。
症状は発疹や目や皮膚のかゆみ、下痢や嘔吐、はなみず、咳、ひどいものだと呼吸困難や失神など様々です。適切に診断し、原因となる食べ物を摂取しないようにする、間違えて摂取してしまった場合の対応方法をご本人、ご家族ともに確認しておくことが大事です。
TOP