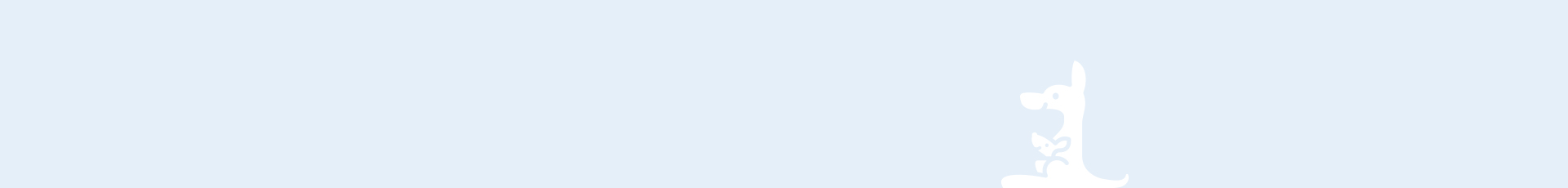
一般小児科
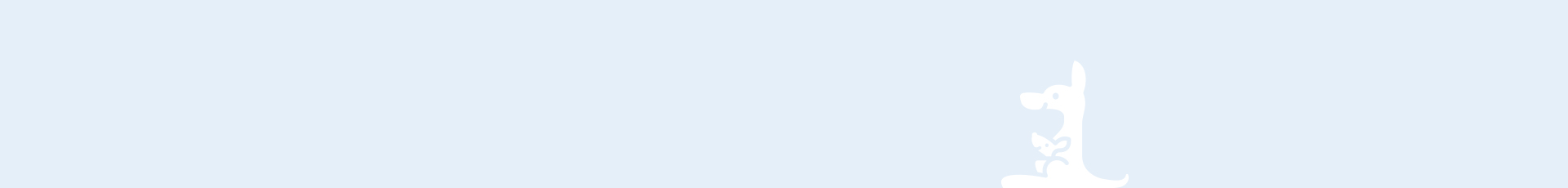
一般小児科
小児科はこどもの多様な疾患に対応する診療科です。小児の病気は症状の訴えがなかったり、わかりにくかったりという特徴があります。また、発症や進行が急であることが多く、病気の種類も多数存在します。こども特有の感染症もあり、感染症にかかりながら免疫を得ていくために、一生で最も感染症にかかることが多い時期といえます。
こどもの病気は大人とは様々な点で異なるため、日ごろから状態や平熱、顔色などをよく観察しておくことが大切です。「いつもと違う」という親の直感が、重大な病気の発見につながることもよくあります。お子様の症状やお困りのことは何でも相談をお受けします。育児相談や予防接種など幅広く対応していますので、お気軽にご来院ください。
感染症とは、体内に細菌(バイ菌)、ウイルス、真菌(カビ)、寄生虫などの病原体が体内に侵入し感染することで、何かしらの症状が生じる状態のことです。感染症の中には、風邪、胃腸炎、中耳炎、溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、みずぼうそう、おたふく風邪、インフルエンザ、百日咳、マイコプラズマ、とびひ(伝染性膿痂疹)などがあります。
症状は、発熱、呼吸器症状(せき、たん、鼻水、のどの痛み)、耳の痛み、消化器症状(腹痛、下痢、嘔気、嘔吐)、湿疹など病原体ごとにさまざまです。
治療法は症状をやわらげる治療(対症療法)と病原体をやっつける治療(抗菌薬、抗真菌薬など)があります。細菌感染症には抗菌薬(抗生物質)を使用しますが、風邪などのウイルス感染症の多くは病原体をやっつける治療法はなく、対症療法で症状をやわらげつつ、お子様自身の免疫でウイルスを退治するのを待ちます。
突発性発疹は、2歳までにほとんどの人がかかる頻度の高い感染症です。発症すると、突然38℃以上の高熱が現れますが、食欲がない、機嫌が悪い、ぐったりしている、といった全身症状が目立たないケースが多いことも特徴です。通常、発熱は3〜4日で自然に治まりますが、解熱後に全身(顔や腕、脚など)に発疹が多数みられます。発疹は2~10㎜程度の小さなプツプツとした紅斑で、3~4日ほどで跡を残さず消失します。かゆみや痛みなどは伴いません。
高熱が5日程度続く感染症です。目にも感染しやすく、目の充血、目やにを伴う場合は、プール熱とも呼ばれます。急な発熱からはじまることが多く、39~40℃くらい上がることもあります。初期に熱だけのことも多く、途中から喉の痛みや咳、鼻水が出ることがあります。治療薬はなく対症療法を行います。感染力が強いため、熱が治まっても2日程度は幼稚園や学校などは休むようにしましょう。
夏かぜのウイルスで起こる病気で、手のひら、足のうら、口の中に水疱(水ぶくれ)ができるのが特徴です。生後6か月から4~5歳の乳幼児に多く、飛沫感染や便から排泄されたウイルスが手に付着し経口感染することもあります。
口の中の発疹は盛りあがったり、水をもったりするブツブツで、破れて潰瘍になると、刺激のある物を食べるとしみて痛がるようになります。口内の症状に少し遅れて、手のひら、足のうらなどに生米くらいの水疱性の発疹ができます。まれに髄膜炎を合併することがありますので、高熱や頭痛、ひきつけ、嘔吐などの症状が伴う場合は、すぐに受診しましょう。
夏かぜのウイルスで起こる病気で、水疱ができて発熱がある点で、手足口病と似ていますが、手や足には発疹は出ず、口だけに症状が現れます。乳幼児の間で流行し38~40℃の高熱が2~3日続きます。のどの奥に小さな水ぶくれができ、痛みがあり食べることが困難になります。治療は喉の痛みを抑える薬の服用などで対症療法を行います。
ムンプスウイルスによる感染症で、主な症状は熱と耳下腺の腫れです。耳の下から頬やあごなどが腫れて痛みます。まず片方が腫れ、2~3日後にもう片方が腫れてくる場合もありますが、片方だけ腫れることもあります。耳下腺の腫れと同時に発熱がみられることもあり、3日目くらいが腫れ・熱のピークとなります。1週間程度で治まります。かかりやすいのは幼児期後半なので予防接種は2~3歳までに済ませておくとよいでしょう。
インフルエンザウイルスによる急性熱性感染症で、通常、寒い季節に流行します。感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、38℃以上の突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの症状がこれらに続き、およそ1週間で軽快します。通常のかぜ症候群とは異なり急激に発症し、全身症状が強いことが特徴です。
胃腸炎のほとんどはウイルス感染(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)で、一部に細菌性(カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌など)が見られます。ウイルスが付着した料理を食べたり、手指についたウイルスが口に触れたりすることで感染し、冬場、幼稚園や小学校などで集団発生することも少なくありません。症状は下痢、腹痛、嘔吐、発熱が多く、治療は脱水を予防し、症状に合わせた内服薬を服用します。
肺にマイコプラズマという微生物が感染することで起こります。若年者に多く、熱が下がらない、咳がひどいといった症状が続きますが、比較的元気なことも少なくありません。胸のレントゲンでは、暗い肺野の中に、白っぽい肺炎の影が認められます。発疹を伴うこともあります。抗生物質を中心とした薬物治療が行われます。
溶血性連鎖球菌(溶連菌)による感染症で、かぜと同じような症状を起こします。急性咽頭炎を起こした場合、発熱してのどが痛くなり、のどや口の中が真っ赤になります。舌にいちごのようなブツブツができることもあります。食べ物を飲み込んだだけでも痛みます。治療によって2~3日程度でのどの痛みや発熱、発疹などの症状は治まります。
水痘・帯状疱疹ウイルスが咳やくしゃみで飛び散り、それを吸い込んだり(飛沫感染)、水疱が破れて出てきた液に触ったりする(接触感染)ことで起こります。37~38度程度の発熱とともに、赤い小さな発疹が現れます。発疹は、水が入ってふくらんだ水疱になり、かゆみが強くなります。水疱は2~3日でしぼみ、黒褐色のかさぶたになり、1週間程度で治ります。水ぼうそうは治ってもウイルスは長く体の神経節細胞内に留まっているため、何年か後に帯状疱疹(帯状ヘルペス)という病気を発症することもあります。
うんちが長い間でなかったり、でにくい状態を便秘といいます。排便の回数が少なくなくても、うさぎのうんちの様な小さくコロコロした便しかでない時や少量の柔らかい便しかでない時は腸の中に便が貯まっている可能性があります。さらに、便秘による症状があらわれ、治療が必要な状態を便秘症といいます。
症状とは腹痛や腹部膨満(お腹が張っている)、排便する際に痛みや出血が伴う、うんちが出ないことによる不安などがあります。
小児期で便秘になりやすい時期は
が知られています。
便秘症の治療の目標は、「便秘でない状態」にして「その状態を継続する」ことです。
治療法は
にわかれます。
薬物療法として腸の中に水分を保持することで便中の水分を増やして便を柔らかくするタイプの薬がよく使用されています。規則的に便が出るようになってすぐ内服をやめてしまうと、再発をすることがあるため、半年以上かけて薬を中止していきます。
TOP